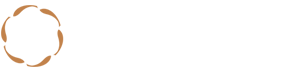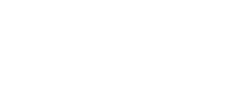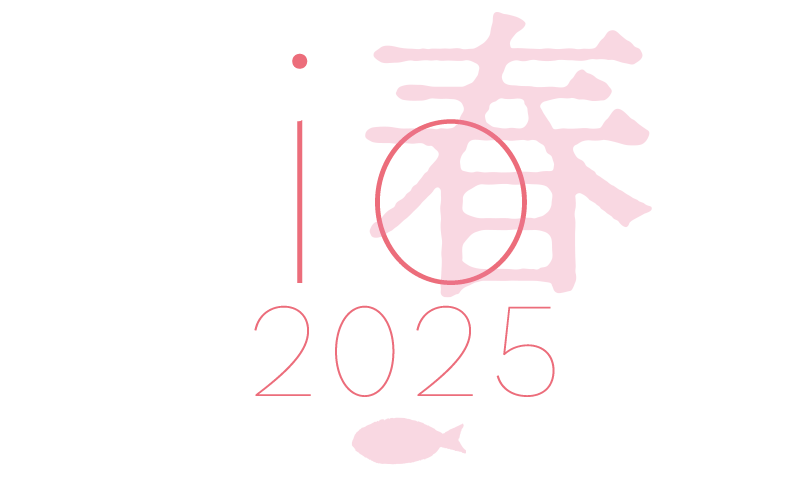
赤染衛門と7月の氷魚
昨年の大河ドラマ「光る君へ」の主人公は紫式部だった。 千年の時を超えるベストセラー『源氏物語』の著者である。ドラマが進むにつれて、凰稀かなめが演じた赤染衛門(あかぞめえもん)が気になった人も多いのではないだろうか。
衛門は、藤原道長の正妻である源倫子とその娘の彰子に仕え、紫式部、清少納言、和泉式部らと親交を結んだ優れた女流歌人だった。彼女の夫は尾張守大江匡衡(おおえのまさひら)。藤原道長が栄華を誇った時代に生涯を送った人物だ。尾張守在任中は大江川開削をおこない、尾張学校院を再興し、地域の教育の向上に努めている。
『赤染衛門集』に、夫の任地に下る途中、7月朔日頃に逢坂の関を越えて大津から舟で琵琶湖を渡り、朝妻に泊まったことが書かれている。
あざぶといふ所に泊まる、その夜、風いたう吹き、雨いみじう降りて漏らしぬ所なし、頼光が所なりけり、壁に書き付けし
水増さりてそこに二三日ある程に、氷魚(ひお)を得て来たる人あり、「この頃はいかであるぞ」と問ふめれば、「水増さりてはかくなむ侍」と言へば
「あざぶ」とは「朝妻」。米原市朝妻湊の辺りである。当時、美濃方面、北陸方面に通じる航路となっていた。
現代……、近江で氷魚といえば鮎の幼魚をいう。氷のように体が透きとおっていることから「氷魚」と呼ぶ。大きさ2〜3センチの繊細で美しいガラス細工のような魚だ。氷魚が捕れるのは12月〜3月頃で5月頃には小鮎と呼ばれるようになる。衛門の尾張への旅は7月。旧暦で1ヶ月ほどズレていたとしても、氷魚とは…? おかしな話である。
琵琶湖には川を遡上し大きく成長する鮎と、遡上せずに一生を湖ですごす鮎がいる。湖ですごす鮎は成魚でも10センチ以下と大きくならない。この鮎を「小鮎」と呼ぶ。小鮎は日本列島各地の鮎とは異なり、琵琶湖にだけ棲息する鮎だ。
衛門は、増水して2〜3日滞在していると、氷魚を捕って持って来てくれた人がいて、7月なのに「今頃どうして氷魚が捕れるのですか」と疑問に思い尋ねると、氷魚を届けてくれた人から「増水すると捕れるのです」と返答があったと記しているのである。
衛門は文芸に秀でた才気溢れる女性である。琵琶湖の氷魚のことは承知のうえで尋ねたのだろう。氷魚を持って来た人は「増水すると…」と弁解した。彼は都の人に喜んで欲しかっただけなのだ。旅の空、衛門は土地の人とのちょっとした交流を楽しんだのではないだろうか……。衛門が7月の氷魚を愛でる様子が目に浮かぶ。いかんせん、大河ドラマを観てしまってからは凰稀かなめになってしまうのである。
春先から初夏にかけて、琵琶湖の小鮎漁は最盛期をむかえる。あゆの店きむらでは、朝一番に捕れた鮮度抜群の小鮎を、熟練した職人が小さな釜を用いて直火で少しずつ、数時間つきっきりで炊きあげている。
衛門はどんなふうにして味わったのか気になるところだが、『赤染衛門集』には記されていない。
春を告げる「本もろこ」

初春、仲春、晩春を三春という。立春から立夏の前日までの期間で、2月4日頃~3月5日頃を初春、3月6日頃~4月4日頃を仲春、4月5日頃~5月5日頃を晩春。「もろこ」は三春の季語である。
昼酒もこの世のならい初諸子 森澄雄
かつて初諸子に至福を味わった文人墨客は数知れず、春に産卵のため群れを成して沿岸を回遊するホンモロコを狙う釣舟が湖に並び、湖岸には釣り人が等間隔に糸を垂れる風景は春の風物詩だった。
諸子釣り琵琶湖狭しと並びたり 高浜虚子
筏踏んで覗けば浅き諸子かな 高浜虚子
今は失われた琵琶湖の記憶である。
ホンモロコは琵琶湖固有種で、産卵期は3月~7月。産卵場所は主に湖岸のヤナギの根やヨシなど、沿岸部では水面ギリギリに産卵する。ホンモロコはコイ科魚類のなかでも身が引き締まり骨もやわらかく絶品、最も美味しいといわれる。特に子持ちのホンモロコは格別。産卵を控えたこの時期は、ふっくらとした身とほのかな甘みを持ち、春の訪れを告げる湖魚として最も相応しい。
照り焼き、味噌焼き、佃煮と食べ方もいろいろだが、なかでも琵琶湖名物といわれたのがホンモロコのおどり焼き。まだ生きているそれを炭火で焼きタレをつけて食べるのだという。森澄雄は、おそらくおどり焼きを愉しんだのではないだろうか。
五感で「味わう」……、人にだけ許された愉しみ方である。近江盆地の雪を戴く山々は黙して語らず、湖面は春に光る。知識に裏付けられた想像力で遠望し、この世のならい初諸子と洒落てみたいものである。