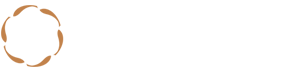とれたての
小鮎をふっくら炊きあげ
お届けいたします。
鮎は春になると海から川を遡上する魚です。寿命1年であるため「年魚」、その独特の香りから「香魚」とも呼ばれています。日本列島の河川に広く分布し、「アア」(岡山県)、「アイ」(富山県・浜名湖周辺・三重県)、「アイオ」(広島県)など、地方名もさまざまです。
ところで、「小鮎(コアユ)」は琵琶湖の鮎のことをいいます。小鮎を鮎の稚魚のことだと思っている人が多いかもしれませんが、「子鮎」ではなく「小鮎」です。
琵琶湖は淡水の海(淡海)ですから川を遡上し大きく成長する鮎もいますが、遡上せずに一生を湖ですごす鮎は成魚でも10センチ以下と大きくなりません。この鮎が「小鮎」です。
小鮎は日本列島各地の鮎とは異なり、琵琶湖にだけ棲息する鮎だからこそ特別なのです。
春先から初夏にかけて、湖の小鮎漁は最盛期をむかえます。琵琶湖には、小糸(こいと)漁・追い叉手(さで)漁・沖すくい網漁・えり漁など十数種の独特の漁法があります。
なかでも「小糸漁」で捕れた小鮎は、煮炊きしたときにふっくら柔らかだと伝わります。
「あゆの店きむら」では、朝一番に小糸漁で捕れた鮮度抜群の小鮎を、熟練した職人が小さな釜を用いて直火で少しずつ、数時間つきっきりで炊きあげています。
びわ湖産天然 小あゆ煮
自然の持ち味を生かして、丹念に煮あげた逸品です。 鮮度抜群・琵琶湖産の天然の小鮎を、時間を置かずに小さな釜で少しずつ、熟練した職人が直火で数時間つきっきりで煮上げています。 仕上がりもふっくら柔らかで、まろやかな味わいに仕上げています。
大地の恵みと湖の恵みの邂逅
「えびまめ」は、琵琶湖のスジエビと大豆を一緒に甘辛く炊きあげた郷土料理です。滋賀県は関西で最も大豆栽培が盛んな地域で、昔は田の畦で大豆や小豆を育てていました。祝儀や法事、祭りなどの集まりで大豆を使用した料理がならび、「えびまめ」もその一つでした。
スジエビは産卵期の春から夏にかけて水深10mほどの浅瀬に生息し、冬に入ると深いところへ移動します。春から夏は「エビたつべ漁」、冬は「沖びき網漁」で捕ります。「たつべ」は専用の「かご」を使った伝統漁法です。たつべの中に仕掛けた餌を求めて入り込んだエビが出られなくなる仕組みになっています。沖びき網漁は、漁船で網を仕掛ける底びき網の一種です。
大豆は「畑の肉、されど肉の害なし」といわれるように、良質な蛋白質に恵まれています。スジエビは殻がついたまま柔らかく炊きあげますので、カルシウムを補い、栄養バランスもよいひと品です。「エビ」のように腰が曲がるまで「マメ」に暮らせるように……の願いはいつの時代も変わりません。
「あゆの店きむら」では、国産大豆と新鮮なスジエビをほんのり甘く、柔らかく炊きあげています。当店自慢の小鮎と合わせた「あゆまめ」とともに、ぜひ、近江の大地の恵みと湖の恵みを味わっていただければと思います。
琵琶湖の小鮎漁は春先から初夏にかけて最盛期をむかえる。湖には、小糸(こいと)漁・追い叉手(さで)漁・沖すくい網漁・えり漁など十数種の独特の漁法がある。なかでも「小糸漁」で捕れた小鮎は、煮炊きしたときにふっくら柔らかだと昔から伝わっている。
琵琶湖の鮎は、夜、湖岸近くで餌を食べ、明け方沖合へ移動する習性がある。この習性を利用した刺し網漁を「小糸漁」という。湖の漁師は「刺網(さしあみ)」のことを「小糸」と呼ぶのでこの名がある。何故「小糸」と呼ぶのかその理由は伝わっていない。小糸は漁の対象とする魚によって、あるいは仕掛ける場所によって網目の大きさや網の丈、色が異なる。ニゴロブナは「イオ小糸」、ビワマスは「マス長小糸」、その他「アユ小糸」「モロコ小糸」など、ウキやオモリの加減も違い、魚の種類と仕掛け方の違いの数だけ小糸が存在する。
小鮎の小糸漁は、夜中に網を仕掛け、日が昇りはじめる頃まで続く。
夜中11時、あゆの店きむら本店から車で15分ほど、宇曽川漁港を小糸漁の船が出る。湖岸線と平行に横30メートル×縦4メートルの小糸を8枚、カーテンを張るように沈めていく。240メートルの網を張り終えるのは午前1時過ぎだ。湖岸から沖合に移動するだろう場所に張った網目に鮎が「刺さる」のを待つ……。小さい鮎は網目を通り過ぎ、大きい鮎は網に進路を塞がれ迂回する。ちょうど頭が入り腹が抜けないサイズの鮎だけが網にかかるのだ。網目の大きさで望むサイズの鮎を捕ることができる……。
小糸漁はこうすれば捕れるという確実なものはない。月が明るい夜はあまり捕れないといわれている。大漁だったりすることもある。あれこれ考え試し、ツボにはまったときにはこの上ない気分だという。日によって違うが、夜が明けるまでに3度、網を張り大漁を願いながら小糸を引き上げる。経験と勘が頼りの漁とはいうが、運を招く漁師の精進も必要なのだろう。


琵琶湖の漁師は小糸網を1枚、2枚ではなく「把(わ)」と数える。「把」には「片手で握る」という意味がある。おそらく、小糸網をまとめ、片手で握ることができるボリュームを単位にしたのではと推測することはできる。本来あったはずの理由、その記憶は失われ、「昔からそうだから」という「把」の単位だけが伝わっていく。
何故だか分からないが、昔からずっとそうしているというのが伝統なのかもしれない。
「あゆの店きむら」では、朝一番、小糸漁で捕れた鮮度抜群の小鮎を、熟練した職人が小さな釜を用いて直火で少しずつ、数時間つきっきりで炊きあげている。
春色の琵琶湖
「鏡を延べたとばかりでは飽き足らぬ。琵琶の銘ある鏡の明かなるを忌んで、叡山の天狗共が、宵に偸(ぬす)んだ神酒(みき)の酔(えい)に乗じて、曇れる気息(いき)を一面に吹き掛けた様に 光るものの底に沈んだ上には、野と山にはびこる陽炎(かげろう)を巨人の絵の具皿にあつめて、只一刷(ひとはけ)に抹(なす)り付けた、瀲?(れんえん)たる春色が、十里の外(ほか)に糢糊(もこ)と棚引(たなび)いている」。
夏目漱石の長編小説『虞美人草』一章に書かれた春の琵琶湖である。明治40年朝日新聞に連載された作品だから100年以上前の琵琶湖だ。
「瀲?(れんえん)」は「さざなみが立ち、光りきらめくさま。 また、水が満ちあふれて静かにゆれ動くさま」をいう。『虞美人草』は現代では難しい言葉も多く、途中で読むのをやめたくなるところも多いが、近江を知る者にとっては、京都から比叡山に登り現れた瀲?たる春色の琵琶湖の描写だけは印象に残るに違いない。実際には観てはいないが、ああこんな感じだろうと、記憶が風景を再構築するのだ。そしてその風景は、同じではない。
比叡山延暦寺は滋賀県大津市にあるが、「古都京都の文化財」のひとつとして世界文化遺産に登録されている。2025年、滋賀県と彦根市は彦根城の世界文化遺産登録を目指している。登録が実現すれば近江は、二つの世界文化遺産を有する都市となる。
春は桜の季節である。
実は、日本の桜の名所のほとんどは、紀元二千六百年記念や戦後復興のまちづくりとして植えられたものだといわれている。日本書紀の紀年に基づき、初代天皇(神武天皇)が即位した紀元前660年を皇紀元年と定め、昭和15年(1940)が紀元二千六百年にあたることから、国威高揚のため各地で式典を行い、国を挙げて祝ったのである。
彦根城は今でこそ桜の名所だが、紀元二千六百年記念の桜よりも更に古く、昭和9年(1934)に吉田繁次郎が植え始めたものだ。彦根がまだ彦根町だった頃である。町会議員だった吉田繁次郎は「古い城下町の味をたいせつにし、大きく伸びる町にするには、観光の町として発展させていくのが、いちばんよいのではないだろうか。そうだ、皇太子の誕生の機会に、彦根城一帯に桜の木を植えて、桜の彦根城にしよう。」(『彦根の先覚』)と夢を持った。寄付を集めソメイヨシノの苗木千本を購入し、繁次郎の夢は現実のものとなった。第二次世界大戦中、金亀公園に植えた桜は切り倒され、一帯はさつまいも畑になり、昭和34年(1959)の伊勢湾台風などで繁次郎の育てた桜の木は半分の500本余りに減ってしまった。その後、彦根城を愛する人々によって植樹が行われ、現在は約1100本の桜が咲き誇っている。
春になると山の神は里に降りてきて桜の木に宿る。花見は、神を迎え、里の美しい風景を愛でながら、豊作と無病息災を願う神人共食の祝祭である。白洲正子の『近江山河抄』に西郷信綱の『古代人と夢』の一文が引用されている。「昔を想い出すことが忘れていた今を想い出すことであるような、そういう想い出しかたがありそうな気がする」。
あゆの店きむらは淡海の食文化を大切に、「そういう想い出しかた」をすることが、結果として世界文化遺産登録の応援につながるのだと信じて疑わない。